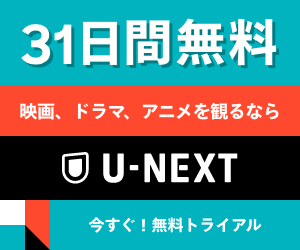大関弾右衛門増虎と下野国黒羽藩
大関和の父・大関弾右衛門増虎
大関増虎(おおぜきますとら)とは、NHKの2026年前期朝ドラ「風、薫る」の主人公のモデルとなった大関和(おおぜきちか)(1858~1932年)さんの父である大関弾右衛門(おおぜきだんえもん)(1827~1876年)のことです。
「増虎」とは諱名のことであり、「弾右衛門」とは通称のことを指しています。よって大関和さんの父の名前を正確に呼ぶ場合には「大関弾右衛門増虎」ということになるでしょう。
なおこの記事では「大関弾右衛門増虎」のことを「大関増虎」と呼称します。
黒羽藩を治める大関家と縁戚関係にあった大関増虎
現在の栃木県大田原市付近の下野国黒羽の地は、南北朝時代から幕末期をまで代々、大関氏が治めていた土地でした。
大関増虎はこの大関氏の縁戚に当たり、黒羽藩第15代藩主の大関増裕(おおぜきますひろ)(1838~1867年)が1863(文久3)年3月に藩主として初めてのお国入りした際に、新しい家老として抜擢された人物でもあります。
そんな大関増虎は、幕末期において様々なエピソードを持つ人物として知られています。
大関増虎 6つのエピソード・逸話
1. 藩政改革のために抜擢された
大関氏は何百年にもわたって同じ地域を治めていたため、ともすれば先例重視で保守的な考え方に流される傾向がありました。
しかし第15代藩主の大関増裕は、もともと大関家の出ではなく横須賀藩・西尾家の出身。さらにその優秀さから幕府では講武所奉行・陸軍奉行・海軍奉行などの幕政の要職を歴任してきた人物です。
その増裕から見て世襲の家老たちは能力を伸ばすことや積極性に欠けるように見えました。その結果、浄法寺頼母(じょうぼうじたのも)・益子右近・五月女(そうとめ)三左衛門・渡辺記右衛門といった家老たちを降格扱いにし、代わりに大関増虎や村上一学を家老として登用。
つまり大関増虎は代々の家老ではなく、その能力を見込まれて抜擢されて家老に選ばれたのです。
2. 財政を立て直すために硫黄の採掘事業に従事した
若い家老として抜擢された大関増虎が主に取り組んだのは、黒羽藩の藩内で産出される硫黄の採掘事業です。
硫黄は当時の小銃弾や大砲の弾を発射するときに使われる黒色火薬の主原料となります。ペリーによる黒船来航以来、幕府や各藩は軍隊の西洋化を進めており、硫黄や黒色火薬の需要が急速に高まっていました。
幕府中枢で軍政を担当していた藩主・大関増裕はこうした世間のニーズを敏感に察知しており、硫黄の採掘と販売によって得た金で黒羽藩の財政改革を成し遂げようとしたのです。
藩主の意図を汲んだ大関増虎は、那須高原の三斗小屋の付近から硫黄採掘の陣頭指揮にあたることになります。
明治維新後も硫黄採掘の事業を続けていた
朝ドラ「風、薫る」では大関増虎のモデルとなった一ノ瀬信右衛門(北村一輝)は「明治維新前に家老職を辞して農家になり、役人への誘いがあっても断り続けている」とあります。
ですが実在の大関増虎は明治維新後も南東北地方で硫黄の採掘事業を続けていました。1918(大正7)年にはその事業の功績が認められ、政府から「正五位」の位階が死後追贈されています。
3. 藩主を諌めて増税を辞めさせた
しかし大関増裕の財政改革は急激な一面もありました。
藩内の高禄の家臣から「借り上げ」という形で禄を差し引いていただけでなく、領民からも1867(慶応3)年からの5年間に限って六分の税率を八分五厘に引き上げようとしていたのです。
この結果、藩内にある11ヶ村の百姓たちが結束して一揆を実行。首謀者たちが処刑されることに。
事の成り行きを三斗小屋で聞いた大関増虎は、幕府の若年寄として江戸に在府していた藩主・大関増裕のもとに急行。一揆の首謀者たちを赦免するよう理非を尽くして説得し、特赦の許可を得て黒羽に帰国。
増虎はそのまま刑場まで走り、刑の執行直前で一揆の首謀者たちの命を救うことになります。結局、刑の執行が中止されたことで増税の話は立ち消えとなりました。
4. 藩主・大関増裕が亡くなったのち殉死をしようとした
「王政復古の大号令」が発せられた1867(慶応3)年、日本中のすべての藩は、新政府に味方するか(勤王)、それとも幕府に味方するか(佐幕)を迫られました。
黒羽藩において、藩主の増裕は幕府の要職を歴任したこともあり佐幕の方針をとるつもりでしたが、弾右衛門以外の家老たちの意見は朝廷に忠誠を尽くす勤王の方針に傾きます。
もし幕府に味方すれば新政府によって黒羽藩はお取り潰しに遭い、しかも大関家は断絶。しかし新政府に味方することは情において忍びないと考えた増裕は自決することを決意。
増裕は自分の気持ちを増虎だけに打ち明けたところ、増虎は殉死を申し出ましたが、増裕から止められ黒羽藩の将来を託されることになります。
その後、大関増裕は狩猟と称して家臣数人と出かけ、金丸八幡宮の林の中において咽頭から後頭部にかけて銃で撃ち抜き、自殺を遂げることになりました。
5. 会津戦争ののち家老を辞職を決意
1868(明治元)年の会津戦争において黒羽藩は新政府軍に味方し、増裕の財政改革によって得られた武器・食料が使われることになります。
このときの黒羽藩の蓄えはわずか1万8,000石の小藩のものとは思えず、戦後に新政府軍から感謝状が送られる程でした。
しかしこの頃になると先代の増裕が進めていた改革は緩み、黒羽藩は会津戦争の前に蓄えていた武器や食料をただ使い果たしただけの状態に逆戻りします。
藩の将来を憂いて自殺した増裕から後事を託されたにもかかわらず、財政改革を頓挫させてしまったことの責任を感じて増虎は家老職を辞し帰農を決意。
そのとき増虎が大関和さんに言った言葉は、朝ドラ「風、薫る」の原案となった「明治のナイチンゲール 大関和物語」でも語られています。
「今日より家禄(二百石)は云うに及ばず、家も屋敷も返上し、明日からは乞食するかもしれぬが、大関弾右衛門の娘と生れし不幸と思いあきらめよ」(『基督者列伝』)
田中ひかる. 明治のナイチンゲール 大関和物語 (p. 9). (Function). Kindle Edition.
6. 慰留され黒羽藩の家知事に
もっとも大関増虎の辞職は増裕の妻・於待(おまち)によって強く慰留されます。そのため増虎は帰農が認められず藩の執政職(家老)から家知事に「降格」という扱いに。
この後、黒羽藩は新政府から永世禄として1万5,000石が与えられ、その際家老たちにもそれぞれ50石が与えられることになりました。
しかし家老から降格し家知事になっていた増虎には、新政府からは何の音沙汰もありません。代わりに増虎の嫡子で幼い大関復彦に対して「一人扶持を与える」という書き付けが与えられただけでした。
当時11才だった大関和さんはこの処置に対して大変怒りを覚えたそうですが、当の増虎は平然と流していたと言われています。
大関増虎のエピソード6選 関連記事と参考文献
大関増虎 死後のエピソード 関連記事
大関増虎は黒羽藩の家老時代に硫黄採掘の事業に従事していたことから、長田銈太郎という明治政府で外交官となる人物と知り合うことがありました。
この長田銈太郎は後年、トレインドナースとなった大関和さんの看護を受けるという不思議な巡り合わせをしています。詳細については下記の記事が参考になります。
大関増虎 参考文献
今回の記事を書くにあたって以下の2冊の本を参考にしています。これらのうち「明治のナイチンゲール 大関和物語」は朝ドラ「風、薫る」の原案にもなっています。