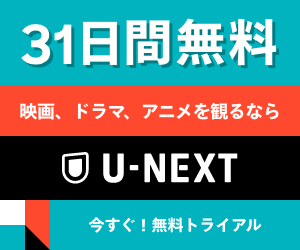小泉チエが物乞いになった理由は上級武士の価値観
「雨清水タエ 物乞い」のモデルは「小泉チエ 物乞い」
NHKの朝ドラ「ばけばけ」の第6週では、主人公・松野トキ(髙石あかり)の実母である雨清水タエ(北川景子)が、松江市内の道端で物乞いをしているという衝撃のシーンが描写されます。
「ばけばけ」の雨清水タエと言えば、モデルは小泉チエであるとして有名ですが、本当にこんなことはあったのでしょうか?
結論を言えば、小泉チエが物乞いをしていたことはほぼ事実でしょう。「八雲の妻 小泉セツの生涯」ではチエの物乞いについてこのように記しています。
こうしたわけで、セツの実母のチエは、ただ食べるために家に残る品々を次々と売り払った末、極端な貧困に陥った他の士族と同じように、人に食(じき)を乞う身となったのである。
(中略)
この家老の一人娘であったチエが人に食を乞う身に陥ったことは、『山陰新聞』が「乞食と迄に至りし」と記し、『西田千太郎日記』に、彼女の身に関して「救済」という表現が用いられている事実に徴して、疑う余地がない。長谷川洋二「八雲の妻 小泉セツの生涯」 潮文庫 108ページから109ページまで引用
雇われて働くことができない価値観に育った小泉チエ
夫・小泉湊が始めた機織会社が倒産したのちは、有力な親戚たちも営んでいた事業が次々と破産に追い込まれ、小泉チエは頼るべき親戚も失っていたのです。
現代人の感覚からすると「ではチエも働けばいいじゃないか」と言うことになるのでしょうが、上級武士の娘が労働をするなどは卑しいものであると言う価値観で育っているため、人に雇われて賃金をもらうという行為ができなかったのです。
「ばけばけ」の雨清水タエは粥を作ることもできなければ、自分で襖を開けたことすらないと描かれますが、これらの演出はまさしく上級武士の価値観を表現していると言えるでしょう。
当時の島根県では元・士族の極端な貧困が社会問題化していた
当時の島根県ではこうした極端な貧困状態に陥った士族たちの存在は社会問題化していました。残念なことに小泉チエのように物乞いをする元・士族というのは決して珍しくなかったのです。
こうした士族の貧困問題に取り組んでいたのは、「ばけばけ」に島根県知事として登場する江藤保宗(佐野史郎)のモデルである籠手田安定でした。
「八雲の妻 小泉セツの生涯」では島根県知事・籠手田安定が県庁に専門委員会を設けて事態の解決を図ろうとした様子が紹介されています。
それによると、松江市及び近村に居住する士族のうち、五十八戸、二百四十人が「乞食するもの」であり、ほかに、三百六戸、千百十三人が「在籍無住にして詳らかならざるもの」であった。「自活の目途なきもの」の割合や、「乞食するもの」の数は、セツとハーンが出会う明治二十四年の初めの頃までには、当然ながら増えていたであろう。
長谷川洋二「八雲の妻 小泉セツの生涯」今井書店 71ページより
小泉チエ 関連記事
小泉チエのエピソードについて
「ばけばけ」の雨清水タエのモデルとなった小泉セツの実母・小泉チエについては下記の記事でも言及しています。合わせて参考にしてください。