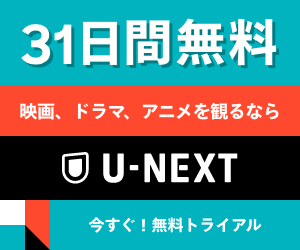朝ドラ「風、薫る」一ノ瀬りんのモデル 大関和さんとは?
大関和さんの人柄とは?
NHKの2026年前期朝ドラ「風、薫る」で主人公・一ノ瀬りん(見上愛)のモデルは、大関和(おおぜきちか)(1858~1932年)さんです。
大関和さんは明治時代に「トレインドナース」となり、明治・大正期を通じて偏見の多かった看護婦という職業の確立に多大な貢献をされました。その活躍から「明治のナイチンゲール」とも呼ばれています。
そんな大関和さんにはその人柄をしのばせるような様々なエピソードがありまり。今回の記事では大関和さんがどんな人だったのかよく分かるように6つの逸話・エピソードをご紹介しましょう。
なお、大関和さんが具体的に何をした人なのかを知りたい場合は、下記の記事を参考にしてください。
また大関和さんの事績について年表形式で知りたい方は下記の記事を参考にしてください。
大関和とはどんな人だったのか 参考文献
以降では大関和さんは、生涯において何をしたのかを紹介いたします。参考とした文献は以下の2冊です。
これら2冊のうち「明治のナイチンゲール 大関和物語」は朝ドラ「風、薫る」の原案となっています。
大関和さんがよく分かる6つのエピソード
1. 決断したらクヨクヨしない
1886(明治19)年、大関和さんは28才の時に植村正久牧師(朝ドラ「風、薫る」の吉江善作のモデル)から桜井女学校(現在の女子学院)内にある看護婦養成所(桜井看護婦学校)に入学して看護婦(トレインドナース)となることを勧められます。
しかし当時の看護婦は世間から「看病婦」とも呼ばれ、「命を売って金儲けをする卑しい職業」という偏見を受けていました。そのため大関和さんは植村牧師から話を聞いたとき、入学に難色を示しました。そのとき大関和さんは植村牧師からこのように悟されます。
この世で病に苦しんでいる人ほど不幸な人はいない。その病人を真心をもって看護することで天なる父の慈愛を示すことのは、これ以上の伝道はないと思う。神の恩を口で説いて感動を与えるより、それを言動にして悟らせるべきではないだろうか
さらに築地の神学校に通っていた従弟に相談をしたところ、「あなたが天使と思う植村牧師の勧めならばそれは神の思し召しだ」と言われ、大関和さんは看護婦養成所に入学することを決意。
「神が自分に道を与えてくれた」と気がついた大関和さんは、植村牧師に入学の意志を告げようとします。
その時間帯は真夜中であったにもかかわらず意気揚々と歩き、植村牧師の自宅に着いたのは何と夜中の午前1時のことだったそうです。
2. 困った人を放っておけない性分
大関和さんには困った人を見たら放っておけないという性分がありました。おそらく元々がそういう考え方の持ち主で、1887(明治20)年3月に植村牧師から洗礼を受けたことで、さらにその性分に拍車がかかったように見受けられます。
1888(明治21)年、看護婦養成所(桜井看護婦学校)を卒業し、「トレインドナース」となった大関和さんは、帝国大学医科大学附属第一医院(現在の東京大学医学部附属病院)で外科看病婦取締となります。
帝国大学の学生寮で火災が発生したとき、無償で看護を引き受けたり(学生はお金を持っていないから)、貧しい入院患者には自分の給料をはたいて世話をすることもあったそうです。
のちに新宿中村屋の創業者となる相馬愛蔵(そうまあいぞう)さんが疥癬で第一医院に入院したときは、トレインドナースでさえも1日1回に塗るのも嫌がる硫黄の塗り薬を、大関和さんは相馬愛蔵さんが早く退院できるよう1日3回も塗っていました。
3. 人目を引く美人だった
大関和さんは周囲の目を引く美人であったと言われています。「大風のように生きて: 日本最初の看護婦大関和物語」の表紙には、1888(明治21)年に大関和さんが看護婦養成所(桜井看護婦学校)を卒業したときの写真が掲載されています。
前列に座っている右から2番目の女性が30才の時の大関和さんです。その「大風のように生きて: 日本最初の看護婦大関和物語」にはこう書かれています。
なお、大関和たちの試験委員をした内科の三浦謹之助、外科の芳賀栄次郎ほか、大沢岳太郎らは、この年の一月に医科大学を卒業したばかりで、新進気鋭の医師として帝大で仕事を始めており、実習生であった大関らとは親しく交流していた。とりわけ美人の誉れ高い和は、彼らの憧れの的でもあった。しかし、徹底してキリスト教主義による看護を定着させようとする和の眼中には、彼らもまた布教の対象としてしか映らなかった。
4. 感情が昂りやすい 「泣キチン蛙(なきちんがえる)」
大関和さんは感情が昂りやすくて涙もろいところがありました。大関和さんは、明治時代から大正時代にかけて「洗濯婆」ぐらいにしか思われていなかった看護婦の社会的地位を向上させるため、内務省衛生局長・後藤新平や警視庁衛生部長・栗本東明に陳情しています。
そのたびに看護婦の重要性、使命の崇高さ、医療に対する貢献を訴えては感情が昂り、ついには陳情の最中に大粒の涙をボロボロとこぼすこともしょっちゅうだったようです。
また大関和さんは看護婦の仕事やキリスト教の伝道などで何かつまずくことがあると、植村正久牧師のところに行っては涙声で愚痴をこぼしていました。
愚痴のたびに泣いている大関和さんを見て、植村牧師は「ナイチンゲール」をもじって「泣キチン蛙(なきちんがえる)」とあだ名をつけていたそうです。
5. 元・家老の娘であった大関和さん 「ノブレス・オブリージュ」の持ち主
孫の大関一郎さんによると、大関和さんは「気位が大変高い人」であったと言われています。ただしここでの「気位が高い人」というのは、単に「プライドが高い」という意味ではなく、「ノブレス・オブリージュ」という意味です。
つまり大関和さんの振る舞いや行動は「高い地位や権力を持つ者は、それ相応の責任や義務を果たすべきである」という考え方に基づいていたと考えられます。
これは大関和さんの父が大関弾右衛門増虎(おおぜきだんえもんますとら)で、下野国黒羽藩の国家老だったことと関係があるでしょう。10才までの大関和さんは「家老の娘」だったのです。
1904(明治37)年ごろ、日露戦争で満洲(現在の中国東北部)の前線で戦う陸軍の将兵のために、大関和さんは慰問袋作りに奔走します。
こういった行動は大関和さんの性分の1つである「困った人を放っておけない」ということも関わっているのでしょうが、一面では「国に報いたい」という「ノブレス・オブリージュ」の精神が表れたものであるとも考えられるでしょう。
6. 金銭にこだわりがない
困ったら放っておけない性分と関わりがあるかもしれませんが、大関和さんは金銭にはこだわりがなかったようです。
1909(明治42)年にキリスト教主義の「大関看護婦会」を立ち上げ、所属している看護婦たちは経済的に自立できるようになりましたが、「大関看護婦会」の経営は常に「火の車」だったと言われています。
この時期になっても経営者の大関和さんは東京の神田にあった「さのや」という質屋の常連客だったのです。
「大関看護婦会」の顧客には政府の高官や大臣、実業家といった上流階級の家庭も多く含まれており、そこから大関和さんは看護料の他に、上等な着物や豪勢な舶来品などをいただくことも珍しくありませんでした。しかしそれらはすべて「さのや」の質草に回っていたようです。
キリスト教が説く慈愛の精神で看護を行う大関和さんのお金に関するポリシーは、「金は天下の回りもの」という妙に日本語に馴染んだフレーズでした。
ちなみに大関和さんは金銭欲だけでなく名誉欲も薄く、日本赤十字社の「フローレンス・ナイチンゲール記章」も断っています。