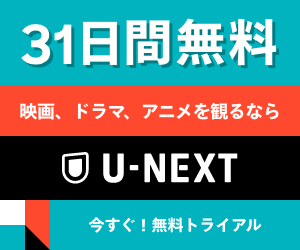妾の存在に苦しんだ大関和の結婚生活
朝ドラ「風、薫る」 一ノ瀬りん モデル 大関和の苦い結婚生活
NHKの2026年前期朝ドラ「風、薫る」で主人公・一ノ瀬りん(見上愛)のモデルは、大関和(おおぜきちか)(1858~1932年)さんです。
大関和さんは明治時代に「トレインドナース」となり、明治・大正期を通じて偏見の多かった看護婦という職業の確立に多大な貢献をされました。その活躍から「明治のナイチンゲール」とも呼ばれています。
大関和さんが看護婦という職業を確立するにあたって重視したことの1つに、看護婦になった女性が経済的に自立できるようにすることでした。この考えの根底には、若き日の大関和さんが経験した苦い結婚生活があったと考えられています。
なお大関和さんとの家族関係を表した家系図については、「大関和 家系図 大関和の家族 朝ドラ 風、薫る 一ノ瀬りん」という記事を参考にしてください。
大関和の結婚相手は黒羽藩の士族・渡辺福之進豊綱
1876(明治9)年、大関和さんは旧・黒羽藩の士族・渡辺福之進豊綱(わたなべとふくのしんとよつな)と結婚。
渡辺福之進豊綱は戊辰戦争に従軍した人物で、明治維新後は陸軍少尉補として東京鎮台に勤務し、さらに陸軍少尉として熊本鎮台・広島鎮台にも勤務した経験がありました(朝ドラ「風、薫る」では渡辺福之進豊綱をモデルとして三浦貴大さん扮する奥田亀吉が登場)。
2人が結婚したときの年齢は大関和さんが18才で、渡辺福之進豊綱が40才。22才の年が離れた結婚でした。
夫・渡辺福之進豊綱には複数の妾がいた
しかし、夫婦の年の差以上に大関和さんを悩ませたのは、渡辺福之進豊綱に複数の妾がいたことです。
結婚した翌年の1877(明治10)年には長男の六郎(ろくろう)を出産しますが、大関和さんは最初の子供であるにもかかわらず、なぜ「六郎」と名付けられるか不思議でした。
実は渡辺福之進豊綱には妾たちとの間にすでに5人の子供をなしており、大関和さんとの子供は6番目であったため「六郎」と名付けられたのです。
長女の誕生後に離婚した大関和
六郎の名付けの理由を知ってショックを受けた大関和さんは、実家に戻ることも考えるようになります。
しかし父・大関弾右衛門が死の直前にまとめてくれた縁談であることを思い出し、一旦は踏みとどまりました。女性が経済的に自立できる見込みが立たなかったからです。
六郎を出産した翌年に再び妊娠したことに気がついた大関和さんは、今度は渡辺福之進豊綱に妾たちと別れるよう迫ります。しかし全く取り合ってもらえません。
そこで出産を理由に実家へ戻り、1880(明治13)年に長女の心(しん)が誕生すると、渡辺家に戻ることを公然と拒否。さらに父・大関弾右衛門の伝手を頼って一家で上京し離婚することを決意します。
ちなみに大関和さんの「盟友」や「バディ」と言われる鈴木雅さんは夫が亡くなるまでは楽しい結婚生活を過ごしていたことを考えると、2人の結婚生活は対照的であったと言えるでしょう。
苦い結婚生活の影響 キリスト教との出会い
英語塾を通して牧師・植村正久と出会う
上京した大関和さんは、植村正度(うえむらまさのり)さんが経営する「正美英学塾」に入塾し、当時流行していた英語を習い始めます。
植村正度さんは牧師・植村正久の弟であり、大関和さんは英語塾に通っているうちに植村正久牧師(朝ドラ「風、薫る」の吉江善作のモデル)の存在を知るようになります。植村牧師は大関和さんが生涯にわたって「師」と仰いだ人物です。
大関和は一夫一婦制を説くキリスト教を信仰
大関和さんは、明治時代初期の大多数の日本人がそう思っていたように、キリスト教は異教あるいは邪教と考えていました。
しかし、あるとき大関和さんはキリスト教が一夫一婦制を説いていることに気付きます。かつての夫であった渡辺福之進豊綱には複数の妾が存在し、苦しい結婚生活を過ごしたことから、この教えは大関和さんの心をとらえました。
この教えが世の中に普及すれば自分のように、夫の不貞に苦しめられる女性はいなくなると考えた大関和さんは、植村正久さんが牧する下谷一致教会に熱心に通い始めます。
のちに大関和さんは植村正久牧師から「トレインドナース」になることを勧められ、1887(明治20)年3月、桜井女学校(現在の女子学院)内にあった看護婦養成所(桜井看護学校)の在学中に、植村牧師の導きでクリスチャンとなりました。
大関和 結婚・結婚相手 参考文献
大関和さんの結婚や結婚生活、さらにはその影響について参考とした文献は以下の3冊です。
- 田中ひかる 「明治のナイチンゲール 大関和物語」 中央公論新社
- 亀山美知子 「大風のように生きて: 日本最初の看護婦大関和物語」 ドメス出版
- 亀山美知子「女たちの約束 M・T・ツルーと日本最初の看護婦学校」ドメス出版
これらのうち「明治のナイチンゲール 大関和物語」は朝ドラ「風、薫る」の原案となっています。
大関和 家族 関連記事
大関和 父
大関和 母
大関和 息子
大関和 娘
大関和 子孫
大関和 妹
大関和 弟
大関和 再婚 再婚相手 関連記事
大関和 再婚 再婚相手
子供を出産したあとに離婚を経験した大関和さんは生涯、シングルマザーを貫きます。しかしその後の大関和さんに恋愛話や再婚話は全くなかったかというとそうではありません。
大関和さんの再婚に関する話題については下記の記事を参考にしてください。