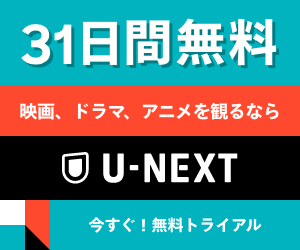看護師(看護婦)として多くの実績・エピソードを持つ大関和
朝ドラ「風、薫る」 一ノ瀬りんのモデル 大関和さんとは
NHKの2026年前期朝ドラ「風、薫る」で主人公・一ノ瀬りん(見上愛)のモデルは、大関和(おおぜきちか)(1858~1932年)さんです。
大関和さんは明治時代に「トレインドナース」となり、明治・大正期を通じて偏見の多かった看護婦という職業の確立に多大な貢献をされました。その活躍から「明治のナイチンゲール」とも呼ばれています。
そんな大関和さんには、看護婦(現在の看護師)として多くの患者の看護をしてきた実績やエピソードが残されています。今回の記事はその実績やエピソードを中心に紹介をいたします。
大関和 看護師としてのプロフィール 参考文献
以降の文章では大関和さんの看護師としてのプロフィール・実績を紹介します。参考とした文献は以下の2冊です。
これら2冊のうち「明治のナイチンゲール 大関和物語」は朝ドラ「風、薫る」の原案となっています。
大関和 看護師としての看護実績
大関和 看護師(看護婦)としてのプロフィール
| 西暦(和暦) | 年齢 | できごと |
|---|---|---|
| 1887(明治20)年 | 29才 | 1月に桜井女学校(現・女子学院)内の桜井看護学校に入学 |
| 1888(明治21)年 | 30才 | 10月に桜井看護学校を卒業。トレインドナースとして帝国大学医科大学第一医院外科看病婦取締となる |
| 1890(明治23)年 | 32才 | 第一医院外科医局長・佐藤三吉に看病婦の待遇改善に関する建議書を提出。11月に第一医院を退職し、高田女学校の舎監に転ずる |
| 1891(明治24)年 | 33才 | 知命堂病院の看護婦長に就任 |
| 1894(明治27)年 | 36才 | 知命堂病院産婆看護婦養成所の兼任講師となる |
| 1896(明治29)年 | 38才 | 高田を去り、上京。鈴木雅が経営する「東京看護婦会」付属の東京看護婦講習所に講師として参画 |
| 1899(明治32)年 | 41才 | 7月に「派出看護婦心得」を出版。11月に「大日本看護婦人矯風会」を設立 |
| 1901(明治34)年 | 43才 | 「東京看護婦会」を辞職。箱根湯本に引きこもるも、鈴木雅から「東京看護婦会」の経営を引き継ぐ |
| 1908(明治41)年 | 50才 | 「実地看護法」を出版 |
| 1909(明治42)年 | 51才 | キリスト教主義の「大関看護婦会」を設立 |
大関和の看護プロフィール(有名人編)
大関和さんの父親である大関弾右衛門増虎(おおぜきだんえもんますとら)は、大関和さんが10才のときまで下野国にの黒羽藩で国家老をしていました。
そのため大関和さんは、明治時代には「出自が良い家老の娘」と見られ、政府高官や大臣といった上流家庭から派出看護を要請され、看護料以外に上等な着物や舶来品を受け取ることもたびたびだったようです。
そんな大関和さんが看護した「有名人」やその家族にはこんな人たちがいます。
| 時期 | 患者名 | プロフィール |
|---|---|---|
| 1888(明治21)年 | 三宮八重野 (さんのみややえの) | 乳がんの手術のため第一医院に入院。宮内省式部官・三宮義胤の妻 |
| 1889(明治22)年 | 相馬愛蔵 (そうまあいぞう) | 疥癬の治療のために第一医院に入院。のちに新宿中村屋を創業 |
| 1889(明治22)年 | 長田銈太郎 (おさだけいたろう) | 自宅への派出看護を依頼した内務参事官。大関弾右衛門と知り合い |
| 1894(明治27)年 | 瀬尾ソノ (せおその) | 腸チフスのため付き添い看護。知命堂病院院長・瀬尾原始の妻 |
| 1896(明治29)年 | マリア・T・ツルー (まりあ・T・つるー) | 体調不良のため付き添い看護。女子学院の設立と経営に尽力 |
| 1896(明治29)年 | 児玉松子 (こだままつこ) | 出産後の付き添い看護。陸軍中将・児玉源太郎の妻 |
| 1896(明治29)年 | 後藤象二郎 (ごとうしょうじろう) | 心臓の病気のため付き添い看護。逓信大臣 |
大関和の看護プロフィール(感染症・事故編)
看護師としての大関和さんは個別患者の看護にあたっただけではなく、感染症(当時の言葉では伝染病)の拡大防止や事故の救護にもあたっています。
赤痢の村でトイレの衛生改善
大関和さんが知命堂病院に赴任していた頃、高田の近隣の農村で赤痢の防疫をするよう、新潟県からの依頼が院長の瀬尾原始の元に入ります。このとき大関和さんは数名の看護婦と共に村に向かうことに。
このとき大関和さんが行ったのは看護だけでなく、「避病院」と言われた隔離施設の衛生改善も含まれていました。特に厠(かわや)と言われたトイレの衛生改善に力を入れ、てんでばらばらに出されていた排泄物を1箇所にまとめ、穴を掘ってすべてに土を被せるようにします。
こうした大関和さんの発案によるトイレを中心とした衛生改善は、赤痢による死者を大きく減らすことに貢献しました。
日露戦争祝勝大会での救護
1904(明治37)年5月、日露戦争の1つである「鴨緑江の戦い」で日本軍が勝利すると、日比谷公園で新聞社主催の祝勝大会が開かれることになりました。
この大会では10万人とも呼ばれる市民が参加することになりますが、皇居の馬場先門(現在の東京都千代田区)で大混乱が起こり、25人の圧死者を出すという大惨事が発生します。
あらかじめ婦人矯風会から看護婦として派遣されていた大関和さんは、救護鞄を抱えて橋の欄干から群衆の真ん中に飛び込み、次から次に死傷者を抱き起こして救い出していきます。
さらに警官が後から後からと押し寄せる群衆を制止できないと見るや、大関和さんは警官に向かって「貴官の剣を貸し給え」と絶叫したというエピソードも残っています。